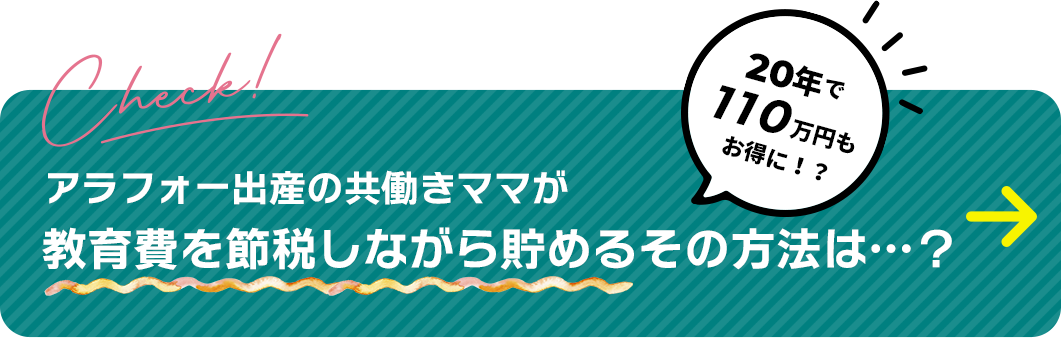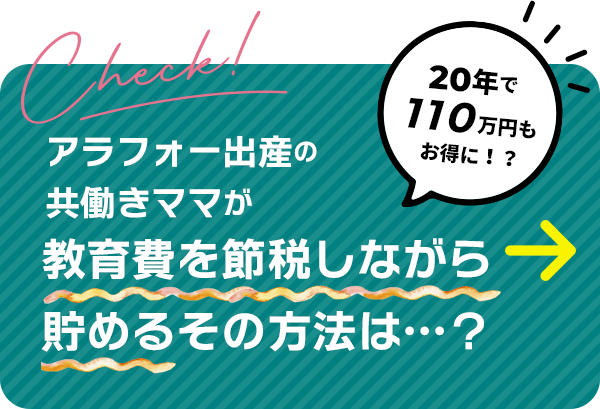2025.02.20(Thu)
【比較】年金の繰り下げ受給はお得?『年金額を増やすこと』と『運用資産の活用すること』を比較してみた
社会保障制度 / 老後資金・確定拠出年金(iDeCo) / 資産運用ライフプランを日々作成していると、『老後資産が明らかに足りなくなりそう…』なんていう結果になることもあります。
考えられる対策の候補をいくつか考えるのですが、その一つが年金の繰り下げ受給をすること。
確かに一カ月繰り下げれば、受け取れる年金額は0.7%増加、つまり5年間繰り下げれば受け取りは年金額の1.42倍(税引前)になり、それが終身続くことを考えると、これは大きい。
ライフプランで試算してみると、繰り下げない場合よりも良い結果に見えることが多いので、これまでは『老後資金に困ったら→年金の繰り下げ受給!』とまず試していました。

しかしここ最近、運用資産・経験・スキルが十分にある方々のご相談の機会があり、ちょっと『それは短絡的過ぎるかも…』と考え直したりしています。
65歳以降も収入があるケースもあるでしょうが、今回は老後資産の準備に関して、以下の2ケースでどちらが将来的に有利になりそうか?について比較をしてみたいと思います。
- CASE① 65歳で年金を受け取らず繰り下げ、年金額を増額。
- CASE② 運用資産もあるが65歳で年金を受け取り開始。
年金の繰り下げ受給のメリット
そもそもですが、年金の繰り下げ受給とは、通常65歳から始まる年金の受給開始時期を66歳から75歳までの間で遅らせることができる制度です。
年金繰り下げをすると、繰り下げた期間に応じて年金額が増額されます。
-
増額率:1ヶ月の繰り下げにつき0.7%の増額。
-
増額目安:70歳まで繰り下げると年金額が1.42倍に、75歳まで繰り下げると、最大1.84倍になる。
-
永続的な増額:増額された年金額は生涯にわたって受給できる。
- 安定性:株式投資などと異なり、元本割れのリスクがなく、年金の増額が保証されている。
年金の繰り下げ受給は、増額が終身に渡って続くことで安心感が得られると考えられます。
年金の繰り下げ受給によるデメリットは
デメリットもいろいろあるのですが、ここでは『運用資産として増やしたものを老後に受け取る場合』と『年金の受給を繰り下げて増やしたものを老後に受け取る場合』を比較した場合のデメリットについてフォーカスしたいと思います。
- 社会保険料や税金の負担増:年金額の増加に伴い、社会保険料や所得税・住民税の負担が増える可能性あり。
- 上昇率:インフレに弱い
- 受給総額の減少リスク:早期に亡くなった場合、65歳から受給を開始した場合と比べて総受給額が少なくなる可能性あり。
社会保険料や税金の負担増について
年金を繰り上げ受給することで年金額が増加→税金・社会保険料も増額します。結果、手取りが思っているよりも増えないこともありえますよね。
一方で運用資産の取り崩しと比較すると、例えばNISA口座や特定口座(源泉徴収ありで確定申告しない)で得た運用益があっても社会保険料に影響はありません。
NISA口座であれば運用益だって非課税になります。
年金を増額せず、運用資産を必要に応じて取り崩して生活する方が税・社会保険料の負担が少なくなると考えられます。
特に年金から引かれるものに関しては、税金よりも社会保険料の方が大きい割合を占めるケースが多いです。
インフレ(物価の上昇)の影響について
ここ数年続くインフレ。贅沢とかそういうレベルではなく、スーパーなんかで買い物するしていても「高いなぁ」と感じることも増えました。
年金は、ある程度であれば物価の上昇に伴って受取額が増える可能性があります。

では年金額の増加率はインフレにどの程度ついていけているのでしょうか?
『物価と同じくらい?』と期待したいところですが、そこまで期待できそうにありません。
例えば令和7年度の年金額の増加率は1.9%でインフレ率(2.7%)ほど高くはありません。(参考:厚生労働省)
詳細な理由はここでは書きませんが、年金額の決定要因は、直近の物価の上昇だけでなくこれまでの物価の変動率や平均寿命の延びによる調整、現役世代の賃金の上昇などが考慮されているからです。(詳細はこちら)
一方で、運用だったらどの程度インフレに対応できるのか?気になるところですが、『どんな資産クラス(株か債券かなど)で運用するか?』にもよるので『資産運用=インフレに強い』と言い切ることはできません。
しかし一般的には株や不動産などはインフレに強い資産(物価の上昇とともに資産価値も上がる傾向にある資産)と言われており、例えば、先進国の株(MSCI指数)の直近20年のリターンは約11%です。
資産運用の結果は、どんな運用資産で運用するか?や運用期間にもより変わってきます。そして元本割れする可能性もあります。(長期分散投資であればその可能性は著しく減少しますが)
ただ少なくともこの20年でいえば、世界株の平均的なリターンはインフレ率をはるかに超える上昇率で、インフレがあっても資産の目減りをへらす効果があった(むしろインフレ以上に増えた)と言えます。
年金の受取総額が少なくなることのリスクについて
最後に年金の受取総額が少なくなることのリスクについて考えてみましょう。
年金の受取を繰り下げること、それはすなわち『65歳以降に年金を受け取らない期間があること』に他なりません。
つまり繰り下げていた後は年金額は増えますが、繰り下げている間は年金を受け取らないので、もし受け取り開始から数年で死亡してしまった場合、結果的に受取総額が少なくなってしまうこともあり得ます。(ちなみに損しないためには、年金受け取り開始から約11年9カ月間生存して年金を受け取ることが必要です。詳細はこちら→)
そのような可能性を考えると、年金の受取の繰り下げを検討するにはある程度健康状況も考慮する必要があると言えます。
しかし人の寿命とはわからないもの。正直、一か八か感がぬぐえないことは否定できません。

一方運用資産である場合は、運用していた資産を使い切れなかった場合でも子や孫に相続させることができます。
形成してきた資産が活かされるという点においては、こちらも運用資産にメリットがあると考えていいでしょう。
まとめ
年金を繰り下げ受給することは、増額された年金を終身受け取れることで大きな安心感を得られる面は確かにあります。
メリットを感じる人も確かにいるでしょう。
でも、運用スキルや経験がある人にとってもそう言えるでしょうか?
将来的に今のようなインフレが継続したり、さらに高いインフレ率になる年だってないとは言えません。
年金資産が老後資産のメインになってしまうと、インフレ率の上昇に対応しきれない資産ばかりになってしまい、経済的に苦しい生活を強いられる可能性も十分あり得る…ということになります。
今後も税制や社会保険の制度の改正は継続的に行われるでしょうが、個人が自身の資産運用を経験し、運用スキルを高めていくことは、将来的な選択肢を確実に増やしていくと確信しています。
年金の繰り下げ受給に関しては、様々なことを考慮した上で慎重に検討することが欠かせません。
今後は『運用資産、経験、スキルがあるか無いか』が人生にさらに大きなインパクトを与えることになりそうです。
おすすめの記事
-
老後資金・確定拠出年金(iDeCo)  2020.12.01
2020.12.01老後資金はいくら必要?夫婦で必要なお金を計算する方法。
アラフォーでの出産となると、教育費も気になるところではあります。 しかし、30代よりもぐっと『老後』..
-
ライフプラン / 住宅 / 資産運用  2020.06.26
2020.06.26住宅ローンの頭金で支出大!貯金はいくら残す?運用中資産はどうする?
住宅の適正購入額を知るために、ライフプランを立てる30代40代の共働き世帯は増えてきています。 それ..
-
保険 / 貯蓄 / 資産運用  2019.02.06
2019.02.06保険で貯蓄の大部分をすることはやめましょう。
『えっと…。老後はアメリカに移住されるご希望ってございましたか?』 『いえ、特に考えていません。』 ..